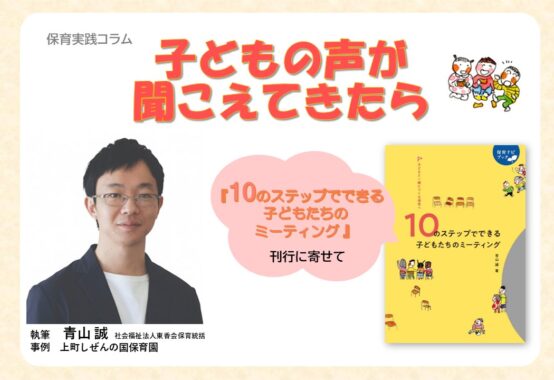「こどもまんなか社会」の実現に向けて、全国の園では様々な取り組みが行われています。そんな中、子ども、保育者、保護者など、関係するそれぞれのワクワクをいかに引き出すかは課題です。そこで『保育ナビ』公式WEBサイトでは、不定期ですが、子どものワクワクに焦点を当てながら、園での様々な保育実践を紹介していきます。

寄稿/佐藤康富(東京家政大学短期大学部 教授)
●プロフィール/佐藤康富(さとう やすとみ):東京家政大学短期大学部 教授。川崎市子ども・子育て会議 委員。著書に『写真とコメントを使って伝えるヴィジブルな保育記録のススメ』(鈴木出版)、『探究心を育む 保育内容「環境」』(大学図書出版)など。
1. 様々な可能性を広げるドキュメンテーション
多くの園で制作されているドキュメンテーションは子どもの姿や保育の様子を保護者に発信するツールとして利用されていることが多いのではないだろうか。
ここで紹介する、東京都中野区の区立丸山保育園でのドキュメンテーションの実践は、その役割を超え、新たなツールとして活かされている。
まず、子ども自身が自分の可能性を広げ、生きる自信を育む、その有効なツールとしてドキュメンテーションが活かされている例を見ていきたい。
2. 子どものウェルビーイング 子ども自身が作るドキュメンテーション!
わが国で、子どもがドキュメンテーションを自ら作る事例は稀であるといってよいのではないだろうか。
丸山保育園では、ドキュメンテーションを保護者に発信するだけでなく、子どもと共有することを心がけている。
ここでは、ニュージーランドの、子どもと記録を「再訪問」するという考え方が活かされている。これは、私のドキュメンテーション研修でも強調している点である。もとは、ニュージーランドのテファリキを開発したマーガレット・カー先生(注1)の考え方を活かしたものである。
子どもたちは自分の姿が写ったドキュメンテーションを見ることにより、その時のことや自分自身を振り返る。そして、自分の行為を活かしたドキュメンテーションを創ることを喜ぶのだ。その一例を紹介する。
〈ドキュメンテーション1〉
ひょうきんな自分を表す子ども
〈ドキュメンテーション2〉
作ったカルタをみんなに紹介したくて、
写真を自分で選び、切り取り、配置も自分で決めて作ったドキュメンテーション
〈ドキュメンテーション3〉
年長の子どもたちが自分たちで計画した「おばけやしき」を振り返り、
そのプロセスを子どもたち自身でドキュメンテーション化した




***
年長児たちが大好きな絵本があった。
ある時、その中に登場する“かっぱおやじ”から、いろいろな行事のたびに手紙が届くようになる。やがて、かっぱおやじは、すっかりクラスの一員のような存在になる。
秋の行事ではクラスの出し物として「かっぱジャングル」を作ることになった。
B 君はクラスの集団活動にはなかなか乗り気になれずにいたが、行事に向けてクラスの仲間がそれぞれ道具作りに夢中になっている様子に次第に感化されていく。
そんなある日、B 君が突然かっぱの歌を口ずさみ始めたのである。
何度もくり返し歌っている姿を見て、「これは鼻歌ではない、作詞・作曲したものなんだ!」と担任はハッとした。
そこで担任が B君の言葉を採取し、メロディーを文字で表現した〈ドキュメンテーション4〉。
このかっぱおやじのテーマソングは、その後の劇ごっこの全員歌唱で保護者にも披露することができた。
〈ドキュメンテーション4〉
子どもが歌い出した「かっぱ」の歌をドキュメンテーションのかたちで記録
もちろん、子どもが作るドキュメンテーションはその遊びの到達点ではない。
白井(2025年)は、ロジャー・ハートの「主体性を発揮する梯子モデル」を示して、その子どもと教師のかかわりのバリエーションの豊かさが重要であることを述べている。つまり、ここでの子どもの変容は、突然現れてくるものではない。丸山保育園の保育者たちがドキュメンテーションと格闘したその物語が育んだのである。
保育者自身、はじめは手探りの状態で、だれもが「ドキュメンテーション⁉」と半信半疑からのスタートであった。
しかし、この歩みにこそドキュメンテーションが活きるキーがあるのだ。
注1:マーガレット・カー ワイカト大学名誉教授。ニュージーランドの教育学者
注2:ロジャー・ハート ニューヨーク市立大学 教授。子どもの権利や心理学に関する研究者
協力/中野区立丸山保育園