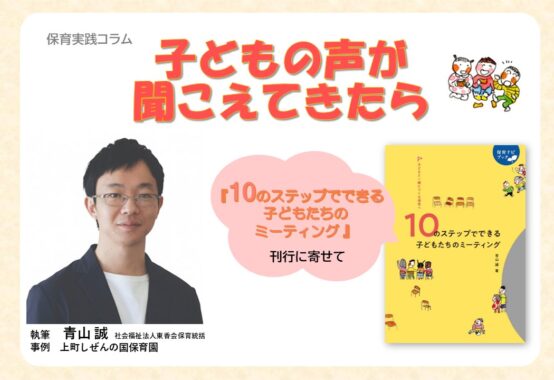「こどもまんなか社会」の実現に向け、全国の園では様々な取り組みが行われています。そんな中、子ども、保育者、保護者など、関係するそれぞれのワクワクをいかに引き出すかは課題です。そこで『保育ナビ』公式WEBサイトでは、不定期ですが、子どものワクワクに焦点を当てながら、園での様々な保育実践を紹介していきます。

寄稿/佐藤康富(東京家政大学短期大学部 教授)
●プロフィール/佐藤康富(さとう やすとみ):東京家政大学短期大学部 教授。川崎市子ども・子育て会議 委員。著書に『写真とコメントを使って伝えるヴィジブルな保育記録のススメ』(鈴木出版)、『探究心を育む 保育内容「環境」』(大学図書出版)など。
★ 子どもの姿を見取る保育日誌の園内研修をきっかけに、ドキュメンテーションの取り組みが始まりました。試行錯誤を重ねるうち、ドキュメンテーション作りのおもしろさに保育者たちが気付き始めます。その制作プロセスにおいて、保育者同士がそれぞれを尊重し合う姿勢が生まれ、子どもを見る目にも変化が生まれてきました。【第2回】から引き続き、保育者のウェルビーイングについて紹介します。
3. 保育者のウェルビーイング ~【第2回】から続く~
1歳児クラスでどんぐり拾いに行った時、保育者がふと思いついて自分の上着を頭からかぶり、おばけになってみた。
子どもたちは大喜び!
〈ドキュメンテーション7〉は、その後もこのおばけの楽しさを子どもが想起し、保育者にその姿を要求したことから生まれたくり返しやイメージの共有のおもしろさを描いている。
〈ドキュメンテーション7〉
1歳児のドキュメンテーションに現れたおばけ


〈ドキュメンテーション8〉
当番保育時の一場面をドキュメンテーションに
夕方、年長クラスに入っていた3歳児クラスの担任が、年長児の発想のおもしろさに感動し、持っていたカメラですかさず撮影。 「これはみんなと共有したい!」と、上の〈ドキュメンテーション8〉に仕立てた。
自分が担当するクラスでなくてもおもしろい場面は写真に残し、職員間で共有したい。保護者にも伝えたい! という気持ちの育ち。このようなことが遠慮なくできる職員関係の風通しの良さは大事である。
***
1歳児も保育室に掲示されたそれらドキュメンテーションを熱心に見ながら、そのおもしろさを反芻し、味わい、日々の生活に活かしている。1歳児なりの保育への参画の姿を現しているとも言えよう。ここには、子どもの姿を見て、保育を創り出す保育者の眼が存在する。
これらイメージを図式化したのが以下の図である。
4. 保護者のウェルビーイング
半ば義務として保育者が配信するドキュメンテーションではなく、保育者が子どもの姿に驚き、おもしろがってできあがったドキュメンテーションの影響力は、子どもの姿のおもしろさ、すてきさ、凄さを保護者にも実感させることになるのではないだろうか。
保護者は、そのようなドキュメンテーションに出合うことで、自らの子どもの成長の瞬間に立ち会えることになる。
以下、〈ドキュメンテーション10〉 は、C君が「工作を大発明」した様子を記録している。これを見た保護者は、わが子の発想と工夫に驚き喜んで、「親戚中でこれを見て盛り上がった」と教えてくれた。
〈ドキュメンテーション10〉
C君の大発明
〈ドキュメンテーション11〉
「もう‼ いっしゅんあそばない‼」

また、〈ドキュメンテーション11〉は、おもしろい子どもの姿を捉えたものである。
この日、子どもたちがトラブルになり、放った言葉「もう‼ いっしゅんあそばない‼」がタイトルとなっている。
この場にいた保育者は、子どもたちの言葉を聞き、「え? 一生じゃなくて、一瞬?」と思っていたら、その言葉を聞いた子どもも、同じポーズをとり、「もう‼ いっしゅんあそばない‼」。まるで劇の一場面にようだった。
なぜ、保育者がこれをドキュメンテーションにしたかというと、その後の子どもたちの行動が決め手だったと言う。子どもだちは一瞬にしてハグして仲直り。「有言実行の素晴らしい場面を伝えたかった」とのことであった。
このようなドキュメンテーションは子どもならではの折り合いの付け方、子どもを、別な言い方をすれば、人の有り様を多面的に見る視座を与えてくれると言えよう。
わが子を通してだけの見方を越え、子どもや人間そのものの豊かさを感じる眼を保護者の中にも育ててくれるのではないだろうか。それが子どもたちと過ごす醍醐味であり、幸せでもあろう。
丸山保育園のドキュメンテーションの実践は、子どもと保育者、子どもと子どもたち、子どもと保護者が共有、共感、認め合い、共創し、新たな自分に出会うものであると言えるであろう。それが、子どもの、保育者の、保育の未来の扉を開けていく原動力になるのではないだろうか。
ここでのドキュメンテーションは単なる伝達を目的とした媒体の役割を越え、子どもを通して、この世界を彩り豊かに見せてくれる、人が豊かに生きるためのウェルビーイングの万華鏡といった役割も、果たしているのである。
〈おわり〉
協力/中野区立丸山保育園