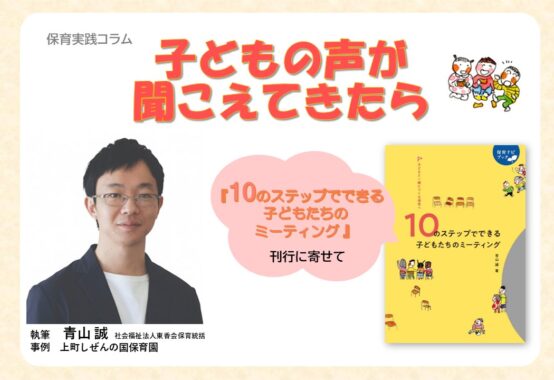◆ 毎回、これからの変化のきっかけにつながるかもしれない保育に関する様々な事柄を取り上げながら、独自の視点から分析します。
新年度を迎えた今回は、これからの保育政策と各園、各法人がどう向き合えばいいのかについて、手掛かりになるような話題を取り上げてみます。
国の保育政策は、これから迎えるであろう社会、あるいは既に迎えている社会を想定してたてられます。その際のポイントは、どういう社会を迎えるのかという想定が適切であるのかどうか、政策が有効に機能して一定の成果をもたらすのかどうか、という点にあります。
つまり、政策の前提と政策の成果が結びつくことが大切になるのですが、これは言うほど簡単なことではありません。1990年代後半から起こった待機児童問題を考えていただければわかります。少子化により出生数が減っているにもかかわらず、女性就業率の上昇によって保育ニーズが高まったことで、需給バランスが崩れて起こったのが待機児童問題です。
これに対して、小泉内閣の下で2001年に待機児童ゼロ作戦が打ち出されましたが、待機児童数が1万人を切ったのが2021年で、一定の成果がみられるまで20年以上かかっています。しかも、昨年の待機児童数は2,567人と、いまだに「ゼロ」にはなっていません。
それくらい大きな保育政策の成果を生むのは難しいのですが、その遠因の1つは地方自治体や保育施設の側にもあると考えられます。待機児童問題に関して言えば、待機児童の解消に向けた取り組みが必ずしも十分ではありませんでした。10年、20年後の心配(定員割れ等)から、受け皿整備に及び腰になった側面があったことは否定できません。そこを埋めたのが株式会社などであったのですが、これに対しても批判的な声が出されました。
そこで、待機児童問題はさておき、これからの保育政策について少し考えてみたいと思います。こども家庭庁は先ごろ、今後の保育政策の在り方に関して「保育政策の新たな方向性~持続可能で質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ」を示しました。こうした形で国が、これからの保育政策を打ち出すことは珍しいことです。
そこでは、保育政策の3つの柱として、❶ 地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実、❷ 全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進、❸ 保育人材の確保とテクノロジーの活用等による業務改善が挙げられています。これらは、2025(令和7)年度から2028(令和10)年度末を見据えた政策となります。
これらの保育政策は、待機児童対策のようにある意味でシンプルな対策がメインではありません。保育機能の維持や保育の質の向上、保育人材の確保といった政策は、具体的な施策や事業を効果的に進めるためには地域の違いや特性などを踏まえる必要があります。
例えば、「地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実」に関して、その1つとして「人口減少地域における保育機能の確保・強化」が挙げられています。「人口減少地域」と表現していますが、これは過疎地を含む地方の人口減少地域だけを意味しない、と筆者は考えています。
都市部においても人口減少地域は存在します。事実、東京23区でも、子ども人口の減少によって園児減に見舞われ、施設閉鎖に追い込まれる保育施設が出始めています。同じ市区町村であっても、その地域内において人口減少の起きているところとそうでないところがあり、地域ニーズは同じではないのです。
保育人材の確保についても、処遇や配置、職場環境の改善によって一定の確保につなげられる地域もあるでしょうが、保育者養成校がなくなったり、アクセスが悪い地域にあっては、処遇改善などの取り組みだけではどうにもなりません。
つまり、これからは、保育政策の前提となる地域の状況を踏まえたうえで、期待される成果につながるような個別最適な政策が求められます。保育そのものが量から質への転換を図らなければならないように、保育政策も全国共通の量的な政策から地域特性に応じた質的な政策が重要になります。これからの保育政策と各園、各法人がどう向き合えばいいのか、答えは1つではないという前提に立って、地域とともに考えることが大切です。
★「保育ナビWebライブラリー」保育のいまがわかる!Webコラム 吉田正幸の保育ニュースのたまご vol.121(4月1日号)で配信した記事です。
★「保育ナビwebライブラリー」では、1か月早くお読みいただけます。