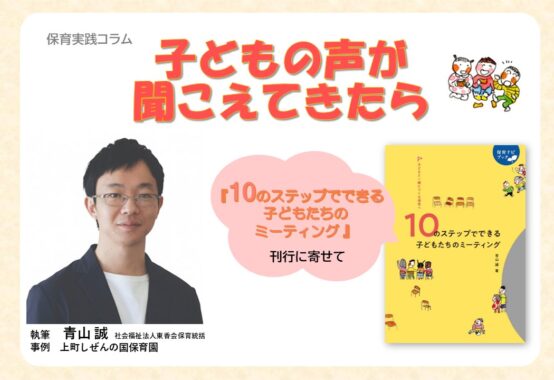◆ 毎回、これからの変化のきっかけにつながるかもしれない保育に関する様々な事柄を取り上げながら、独自の視点から分析します。
保育者の人材確保が依然として大きな課題となっています。少子化の進行によって乳幼児人口が減少し、待機児童もピークアウトしつつあるため、保育人材の需要は減って人材確保の逼迫感も少なくなっているのかと思いきや、むしろ人材難の度合いが強まっているようにさえ見えます。
これは、人材難の要因が複合化していることに加えて、その主たる要因が変化してきていることが影響しているのではないかと考えられます。言い換えると、これからの保育人材確保のためには、人材難に大きな影響を与える新たなボトルネックを少しでも解消し、同時に魅力ある職業・職場であるというイメージアップを図る必要があります。
振り返ると、2015(平成27)年度に子ども・子育て支援新制度が始まる以前から、待機児童問題が顕在化していたこともあって、保育士の人材不足が言われてきました。当時は、保育士養成校の入学定員、入学者数ともにほぼ横ばいの状況で、決して不足していたわけではありません。
ただ、養成校を卒業しても保育所等に就職しない者が3人に1人いたほか、離職率も公私立保育所の平均(2017(平成29)年時点、常勤のみ)で9.4%(私立は10.8%)と決して低くありませんでした。当時のボトルネックは、仕事の大変さに比して給与等の処遇も悪く、2014年(平成26)年当時で全産業平均に比べて11万円(月額)以上も低いという実情にありました。
しかし、その後、人材確保に向けた取り組みが強化され、全産業平均との差は5万円程度にまで縮小しています。昨年夏の人事院勧告に伴う10.7%の処遇改善を考えると、その差はさらに縮まっていると考えられます。
また、働きやすい労働環境、魅力ある職場づくりという点でも、法定外福利厚生の充実や有給休暇の改善、ICTの活用による業務の省力化など、決して十分とは言えないものの、以前に比べれば一定の改善が図られてきています。これに関しては、ICTや保育DXが今後さらに進むことによって、さらなる職場環境の改善が進むものと期待されます。
ところが、足元の現実を見ると、指定保育士養成施設の数は、2019(平成31)年の688校をピークに2024(令和6)年に637校まで減少しています。入学定員数については、2018(平成30)年の6万1,123人をピークに2024(令和6)年には5万2,187人まで減少しています。
これは、単なる18歳人口の減少だけでは説明がつかず。保育職に対する魅力が低下してきていると言わざるを得ません。これまでの処遇や労働条件・職場環境の悪さ、保護者対応を含む業務負担の大きさなどが積み重なっていった影響もあるでしょうが、その根底には保育という職に対する魅力が低下してきていることがあるように思われます。
小・中学生に「大人になったらなりたいもの」を聞くと(第一生命保険の調査)、常に「幼稚園の先生、保育士」が上位に入っていたにもかかわらず、高校から大学・短大、専門学校に進学する段階では「なりたい職業」ではなくなっているという現実があります。
これまで人材確保の基本的な考え方として、筆者は「いれる」(新規採用)、「つなぐ」(就業継続・定着)、「もどす」(再雇用・復職)の3つが柱だと言ってきました。そのためには、「いれる」ための処遇改善、「つなぐ」ための職場環境の改善や魅力ある職場づくり、「もどす」を可能にする多様で柔軟な勤務体制を総合的に目指すことが大切だと説いてきました。
しかし今日、この「いれる」「つなぐ」「もどす」という取り組み以上に、「そだてる」(人材養成)という基本的な要素をより重視した政策や施策が重要になっています。単に重要というより、喫緊の大きな課題と言ってもいいでしょう。
保育人材確保のボトルネックが処遇や職場環境から保育者養成に移りつつあるという現実を受け止め、その問題解消に向けた手立てを多角的に検討し、速やかに対策を講じることが求められます。この問題を克服しなければ、職員配置の改善はもとより、人口減少地域における保育機能の維持のための保育人材確保が困難になります。そうならないためにも、「そだてる」をキーワードにした積極的な取り組みを期待したいと思います。
★「保育ナビWebライブラリー」保育のいまがわかる!Webコラム 吉田正幸の保育ニュースのたまご vol.122(4月15日号)で配信した記事です。
★「保育ナビwebライブラリー」では、1か月早くお読みいただけます。