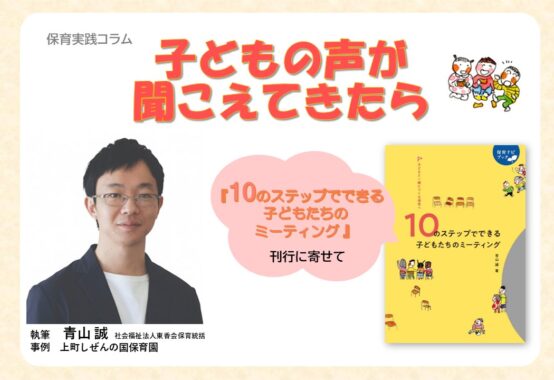◆ 毎回、これからの変化のきっかけにつながるかもしれない保育に関する様々な事柄を取り上げながら、独自の視点から分析します。
政府は先ごろ、「地方創生2.0基本構想」を閣議決定しました。「2.0」ということは、「1.0」があったわけで、こちらのほうは2014年に「まち・ひと・しごと創生法」が施行され、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいて、地方創生に向けた取り組みが始まったことを指しています。
「2.0」と「1.0」の大きな違いは、人口減少の捉え方です。「1.0」は、人口減少そのものを食い止めようという考え方を前提に、東京一極集中の是正や地方の活性化などを目指しました。これに対して「2.0」は、人口減少が続くことを前提に、人口規模が縮小しても経済成長でき、安心して暮らせる地方を創生しようとの考え方を基本にしています。
この考え方を少子化対策に当てはめると、「1.0」は出生数や出生率を引き上げることに重きが置かれ、「2.0」は少子化傾向に歯止めをかけることを目指しつつも、人口減少地域においても保育や子育てなどの「生活必需サービス」を維持・確保することを重視しています。
「1.0」と「2.0」の間には10年あまりの開きがありますが、このわずか10年ほどの間に出生数・合計特殊出生率は約100万人、1.42から68万人、1.15まで低下し、人口増減数も約14万人減から60万人減へと拡大しています。
ちなみに、1972年からの日本列島改造論のときは、出生数・出生率が約204万人、2.14、人口増減数が129万人増でした。半世紀あまりで人口構造が様変わりしていることに驚かされます。
こうした現実を踏まえて、「2.0」基本構想では、保育や子育てについて次のような考えを示しています。
◇ (「2.0」では)人口減少そのものを食い止める視点が前面に出た結果、自然増・社会増を促す施策としての子育て支援や移住促進などが中心となり、地方公共団体間での人口の奪い合いにつながったとの指摘がある。
◇ 地方創生2.0では、少子化対策等により、今後の人口減少のペースが緩まるとしても、当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていく。
◇ 全国どの地域に暮らす若者そして子育て世代にとっても、経済的な不安がなく、良質な雇用環境の下で、将来展望を持って生活できるようにするため、経済的支援の強化、こども・子育て支援の拡充、共働き・共育てを支える環境整備などを一体として進める。
◇ 周産期から産後における健診・分べん等のアクセス確保、保育機能を中心とした総合拠点の整備やこどもの居場所づくり、悩みを抱えるこどもの見守りに取り組む。
この基本構想の推進に当たっては、今後10年間を対象とした総合戦略を策定し、1年、3年、5年の工程表を策定するとしています。今後3年間というスパンは、こども家庭庁が2028(令和10)年度末を見据えて示した「保育政策の新たな方向性」の時期と重なります。そこに盛り込まれた3つの柱の1つである「地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実」では、「保育の量の拡大」から「保育の質の確保・向上」を目指して、「人口減少を含めた地域の課題に応じた保育の量の確保を図るとともに、こどもの育ちを保障するための保育の質の確保・向上の取組を進める」ことが謳われています。
具体的には、教育・保育施設の計画的な統廃合や多機能化、合併・事業譲渡等が想定されています。これに関しては、前号でも述べたように、乳幼児人口の減少という量的な縮小に対して、機能の質と種類(バリエーション)でカバーすることが重要になります。
機能の質と種類ということは、多機能化ということにほかなりませんが、1つの法人や施設が多機能化するだけでなく、ほかの施設や事業者などと連携・協働し、あるいはアウトリーチの発想と手法を組み合わせて、重層的・多角的に展開することが大切です。それが、ひいては地域づくり、まちづくりにつながっていくことで、保育の生きる道が見えてくるのではないでしょうか。
★「保育ナビWebライブラリー」保育のいまがわかる!Webコラム 吉田正幸の保育ニュースのたまご vol.127(7月1日号)で配信した記事です。
★「保育ナビwebライブラリー」では、1か月早くお読みいただけます。