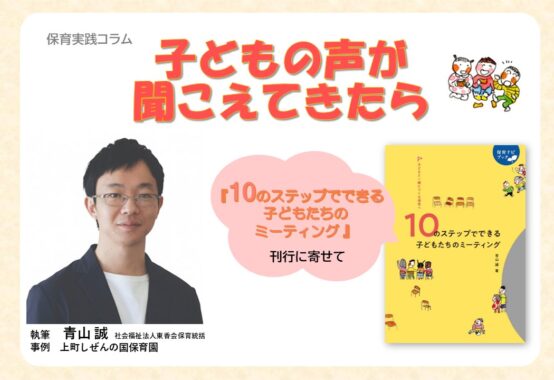◆ 毎回、これからの変化のきっかけにつながるかもしれない保育に関する様々な事柄を取り上げながら、独自の視点から分析します。
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の来年度からの本格実施に向けて、国・都道府県・市町村における準備作業がこれから山場を迎えようとしています。特に、市町村には数多くの準備作業が求められているだけに、需給の見通しが立たないなかで、必要な準備態勢が年度内に整えられるかどうか危惧されます。
こども家庭庁が示した「本格実施に向けた準備事項とスケジュール」によると、来年4月からすべての市町村において実施すべき準備・検討の枠組みとして、❶ ニーズ把握と必要量の推計、「子ども・子育て支援事業計画」への盛り込み、❷ 実施に向けた予算確保、❸ 条例等の制定、改正、❹ 実施事業所の検討・実施に向けた事業所との調整、❺ 認可手続き(市町村児童福祉審議会等への意見聴取等)、❻ 子ども・子育て支援法に基づく施設の確認、❼全体としての提供量の確保と施設整備、❽ 広報周知が挙げられています。
このうち条例等の制定、改正については、この制度を実施するために新たな認可と確認の仕組みを導入することが必要で、市町村は認可手続きに関する規定や確認手続きに関する規定などを盛り込んだ条例を制定しなければなりません。それと同時に、実際に認可・確認を行うために、認可や確認に係る受付・審査を年度内に実施しておくことが必要になります。
なぜならば、 児童福祉法では、市町村長の認可を得て事業を行うことができるとされており、併せて給付の実施主体である市町村が、給付の対象となる施設・事業者を確認することが求められているからです。
認可に関しては、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準も踏まえて、市町村の定めた認可基準に適合しているかどうかを判断することになります。確認に関しては、この事業を行うために必要な経済的基礎があることや、事業を行う者が社会的信望を有すること、社会福祉事業に関する知識又は経験を有することなどを確認することになります。
この事業は、認可を受けた保育所や幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所のほか、地域子育て支援拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施設、児童発達支援センター等においても実施することができるとされているため、認可を受けていない施設・事業者に対して改めて認可・確認を行う必要があります。
なお、既に施設型給付や地域型保育給付を受けている施設・事業者はみなし認可・確認で済むと考えられます。
さらに大変なのは、この事業の対象である未就園児の利用ニーズ(需要)の見込みや、それに対する受け皿(供給)の確保方策を織り込んだ第3期子ども・子育て支援事業計画の見直しを行う必要があるということです。今年4月からスタートした第3期市町村子ども・子育て支援事業計画には、2026(令和8)年度から給付制度として始まる乳児等通園支援事業が盛り込まれていません。
同庁の示した準備事項とスケジュールには、ニーズ把握と必要量の推計、「子ども・子育て支援事業計画」への盛り込みなどと簡単に書いていますが、未就園児家庭へのニーズ調査を行わない限り、正確なニーズ把握はできません。この事業を希望する施設・事業者がどのくらいあるかも、アンケート調査を行って、施設の数や受け入れ可能児童数などを把握しなければ、受け皿となる供給量を算定することは困難です。
しかも、肝心の事業規模等について、同庁の概算要求では事項要求となっており、財政措置の規模や単価、利用上限時間数なども正確にはわかりません。そこが明らかにならないと、市町村も予算を組むことができません。
需要と供給の見通しがわからず、財政措置も不確定というのでは、市町村が需給計画において需要と供給の調整を行うにしても、調整のしようがありません。需要が見込みより少なければ定員割れの施設が出てくるでしょうし、見込みより多ければ未就園児の“待機児童”という不可思議な現象が生じるかもしれません。
さて、こども誰でも通園制度は、あと半年あまりでどのような制度運用になっていくのか、視界不良のなかで最善の体制整備が求められています。
★「保育ナビWebライブラリー」保育のいまがわかる!Webコラム 吉田正幸の保育ニュースのたまご vol.132(9月15日号)で配信した記事です。
★「保育ナビwebライブラリー」では、1か月早くお読みいただけます。