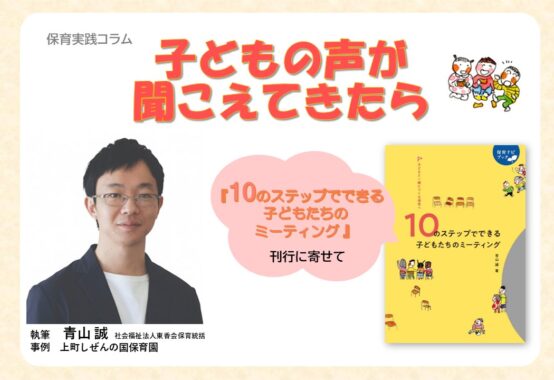◆ 毎回、これからの変化のきっかけにつながるかもしれない保育に関する様々な事柄を取り上げながら、独自の視点から分析します。
こども家庭庁が実施する今年度の調査研究事業の1つに、「延長保育及び夜間保育を含めた保育利用時間等の実態及び早朝・夜間・休日等を含めた保育ニーズの把握に関する調査研究」があります。
これは、子どもたちの保育利用時間の実態や、早朝・夜間・休日等も含めた保育ニーズについての実態把握が十分ではないことから、その実態や保育ニーズの現状等について把握しようというものです。
保育所等においては、8時間の保育を原則としつつ、11時間の開所が求められてきました。子ども・子育て支援制度が始まってからは、1日最大11時間までの保育標準時間、8時間までの保育短時間という2つの利用可能時間を設定し、その前後に延長保育が行われるというのが基本的なパターンとなっています。
しかし、実際に利用している乳幼児が保育所等にどのくらいの時間いるのか、登園時間や降園時間の人数分布はどうなっているのか、といった利用実態はほとんどわかっていません。これらの実態を明らかにすることができれば、職員配置基準の捉え方にも良い意味で変化をもたらすことができるかもしれません。
とりわけ、登降園の前後の時間における職員配置をどう考えるかについて、実態・実情に即した在り方を検討する手掛かりが得られるのではないかと考えられます。これは、“台形”問題と言われるものです。
例えば、朝9時から夕方5時までの8時間を標準的な保育時間とし、この時間帯に全園児が揃って必要職員を配置することを考えてみましょう。その場合、朝7時半から9時までは徐々に子どもたちが登園し、夕方5時半から7時までは少しずつ子どもたちが降園していくことになります。この登降園の時間帯(3時間程度)には、園児が全員揃っているわけではありませんので、職員配置も少なくていいと考えられます。
登園時間に子どもたちが徐々に増え、降園時間に徐々に減っていくわけですから、園児数の増減をグラフにすれば台形になります。問題は、朝夕の台形の「形」です。登園時間帯の早い段階で園児が揃うかもしれませんし、降園時間ぎりぎりまで多くの園児がいるかもしれません。もちろん、その逆もあり得るでしょう。
国の考えは、登降園の時間帯にほぼ半数の園児しかいないという前提で、基準上必要とされる保育士数をカウントしています。けれども、登園時の早い時間に全員が揃い、降園時の遅い時間まで全員がいたとすれば、もっと多くの保育士を配置する必要があります。
また、日中の標準的な8時間についても、実際にはなかなか取れないにしても休憩時間や昼食時間、さらにはノンコンタクトタイムの確保などを考慮すれば、何対何の職員配置基準だけではカバーできず、もっと多くの職員配置が必要となります。加えて、早番・遅番といった職員のシフトを考えると、職員が切れ目なく瞬時に交代しているわけではなく、重なりの部分(バッファ)がありますので、運営基準上も公定価格上も現在の保育士では不足することになります。
これらの状況を勘案すれば、朝夕の登降園時間の在園児数をどうカウントするかという問題をはじめ、休憩時間や昼食時間の確保、ノンコンタクトタイムの保障など、職員の業務負担の軽減やシフト態勢の円滑化といった観点から、職員配置の在り方を改めて検討することが期待されます。
職員配置に関しては、上述した台形問題やシフトの引き継ぎ時間の問題、ノンコンタクトタイムの確保など、従来の職員配置基準の考え方だけでは捉えられない課題があることは確かです。今回の調査研究事業によって、保育利用時間等の実態がどこまで明らかにされるかはわかりませんが、これらの課題が浮き彫りにされ、単なる配置基準の改善だけでなく、職員配置の実質的な見直しにつながることを期待したいものです。
★「保育ナビWebライブラリー」保育のいまがわかる!Webコラム 吉田正幸の保育ニュースのたまご vol.133(10月1日号)で配信した記事です。
★「保育ナビwebライブラリー」では、1か月早くお読みいただけます。