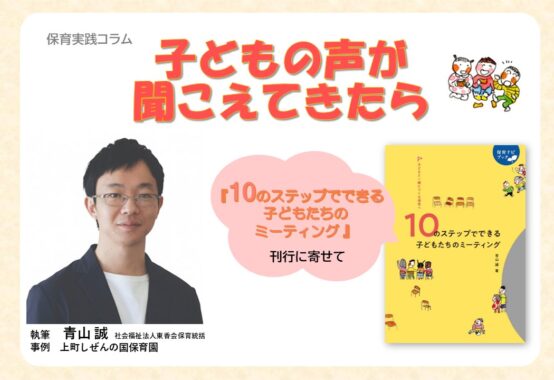◆ 毎回、これからの変化のきっかけにつながるかもしれない保育に関する様々な事柄を取り上げながら、独自の視点から分析します。
こども家庭庁の調査研究事業の一環として、興味深い調査研究報告書がまとめられました。それが、調査研究事業の委託を受けた三菱UFJリサーチ&コンサルティングによる「保育施設等におけるICT 導入状況等に関する調査研究事業」報告書です。
それによると、認定こども園や保育所等(幼稚園は除く)の約99%がパソコンやタブレット機器を保有しており、インターネット接続導入も約94%に及ぶなど、導入台数は別として、ハード面での環境整備はかなり進んでいることがわかりました。
ICT導入率も約80%と意外に高く、機能別に見てみると、「保護者との連絡に関する機能」が約72%、「園児の登園及び降園の管理に関する機能」が約71%、「保育に係る計画・記録に関する機能」が約55%、「指導要録 児童票の作成に関する機能」が約46%、「キャッシュレス機能」が約15%など、機能によって濃淡はあるものの、ICT化もかなり進んでいることが明らかになっています。
こうしたICTの活用効果については、「登降園時間の記録に係る時間・手間を削減できた」が約87%、「当日の出欠席人数を確認する際の時間・手間を削減できた」が約83%、「施設から保護者へ、お休みや緊急時などに電話以外の手段で連絡ができるようになった」が約92%、「紙の印刷、集計、仕分け、配布に時間がかからなくなった」が約86%、「計画の記入・作成にかかる手間や時間が削減できた」が約73%など、一定の成果が見られたと回答しています。
ただ、ICTの重要な役割と考えられている、保育者の働きやすさや業務負担軽減に関しては、「休憩時間をとりやすくなった」が約27%、「1日の勤務の中で、保育室を離れて作業する時間を確保できるようになった」が約30%、「勤務時間内に保育者が保育について振り返ることができるようになった」が約36%などとなっており、必ずしも期待されるような業務改善効果は上がっていないこともわかりました。
一方、政府の第34回「新しい資本主義実現会議」がこのほど開かれ、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の施策パッケージ案が示されましたが、この中で保育分野も取り上げられ、人材確保に向けてさらなる処遇改善を図るとともに、ICT等の活用により業務省力化を促進していくことが謳われました。
とりわけ人手不足が深刻な12業種については、5か年計画の中でより具体的な「省力化投資促進プラン」が示され、12業種の1つとして保育も取り上げられています。そこでは、人材確保のための業務省力化の観点から、ICTの4機能(保育に関する計画・記録、保護者との連絡、登降園管理、実費徴収等のキャッシュレス決済)をいずれも導入している施設の割合を2026年度までに20%とし、職員の事務作業等時間を2026年度比で2029年度までに10%減少させる、といった具体的な数値目標が示されるなど、踏み込んだ内容が盛り込まれています。
ちなみに、上述したICT導入状況等に関する調査研究事業報告書によると、4機能のすべてを導入している保育施設は11.7%(公立8.8%、私立12.6%)となっており、今回示された目標はこれを2倍近く引き上げる計画となっています。
こうした実態や国の動向を見る限り、保育現場におけるICT化や保育DXは急速に普及・拡充していくことになると思われます。
時系列的に見ると、今年度から給付を受けるすべての施設・事業者は職員給与や配置、人件費、収支差、モデル給与などの経営情報を「ここdeサーチ」を利用して報告・届出することが義務化されました。来年度には、「こども誰でも通園制度」の予約管理やデータ管理、請求管理などの総合支援システムが稼働する予定です。「保育業務ワンスオンリー」や「保活ワンストップ」といった保育DXは2027(令和9)年度から本格運用される可能性があります。
見方を変えれば、ICTやDXを職員の業務省力化や園務改善、保育の質の向上などにつなげ、いかに園の魅力づくりに役立てられるかという手腕が問われることになります。これをピンチではなく、チャンスと捉えられるかどうかが、大きな分かれ目になりそうです。
★「保育ナビWebライブラリー」保育のいまがわかる!Webコラム 吉田正幸の保育ニュースのたまご vol.125(6月1日号)で配信した記事です。
★「保育ナビwebライブラリー」では、1か月早くお読みいただけます。