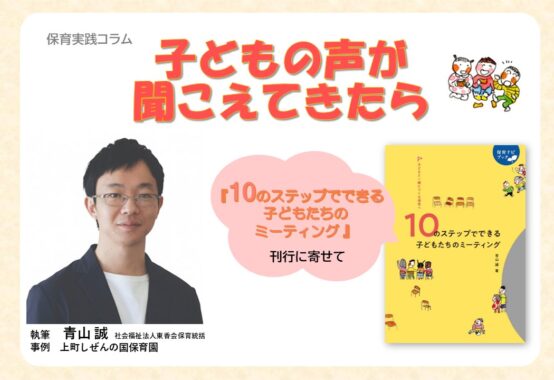◆ 毎回、これからの変化のきっかけにつながるかもしれない保育に関する様々な事柄を取り上げながら、独自の視点から分析します。
昨年1年間の出生数は約68万6,000人、合計特殊出生率は1.15……こんな現実が、厚生労働省が公表した令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)から明らかになりました。
2016年に100万人を切ってから、わずか8年で節目の70万人を下回ったこともあって、多くのメディアが今回の統計情報を大きく取り上げ、少子化の進行が投げかける様々な問題を報じています。
確かに今回の数字(出生数 約68万6,000人、合計特殊出生率 1.15)は衝撃的なものではありますが、予想の範囲内でもありました。今年2月に人口動態統計速報(令和6年 1月~12 月速報の累計)が発表され、前年より3万8,000人近く少ない約72万1,000人であることがわかりました。
この速報値は、日本における日本人と外国人、そして外国における日本人を含んだものですが、今回公表された月報年計は日本における日本人だけを集計したものとなり、両者の出生数は3~4万人の開きが生じると考えられていました。実際、速報値と月報年計の差は、約3万5,000人でした。
本稿ではデータの詳細には触れませんが、婚姻件数も低い水準にとどまり、平均初婚年齢も高止まりしたままですから、未婚化・非婚化、晩婚化・晩産化が少子化を推し進めたことは確かです。加えて、子育て世代の人口が徐々に減っているため、残念ながら出生数が増える要素がほとんどありません。
今年の人口動態統計速報(公表されている1~3月分)を見ても、既に昨年の1~3月を下回っています。そして、来年2026年は、60年ぶりに「丙午(ひのえうま)」の年が巡ってきます。迷信を気にする人は昔より少ないでしょうが、それでも出生という面ではマイナス材料になる可能性があります。
一昨年12月に閣議決定された「こども未来戦略」は、「2030年代に入るまでのこれからの6~7年が、少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンス」と強調していますが、果たして少子化のトレンドを反転させることができるのかどうか、かなり難しいような気がします。
1995年度から始まったエンゼルプランを皮切りに、ほぼ5年おきに少子化対策が見直され、今日の「こども未来戦略」に至るまで、少子化対策が講じられてきました。しかし、結果は、上述の通りです。
そう考えた時、少子化対策には2つの側面、つまり量的な対策と質的な対策があることを改めて認識し、これまで以上に質的な対策に力を入れる必要があるのではないかと思います。量を問題にする限り、教育・保育施設は厳しい状況に追い込まれるばかりです。けれども、質に着目していけば、たとえ人口減少地域であっても持続可能性を高めることができます。
可能性を切り拓くカギは「機能」だと考えます。「機能」は「質」と「量」を要素としますが、「量」の減少を「質」の充実と「質」の豊富さでカバーできます。保育の量(即ち子どもの数)が減ったとしても、保育の質の充実(例えば充実した職員配置)で補い、保育関連事業の質の豊富さ(例えば学童保育や児童発達支援、医療的ケア児など)で強化することが可能です。
こども家庭庁が示した2028(令和10)年度末を見据えた保育政策の方向性の中で、「地域のニーズに対応した質の高い教育・保育の確保・充実」として、❶ 人口減少地域における保育機能の確保・強化(多機能化等)、❷ 保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等)、❸ 保育の質の向上(質の確保・向上の体制整備等)などを挙げているのは、まさに量から質への転換にほかなりません。
少子化が加速する中で、大袈裟に言えば、保育の生きる道は「機能」に着目することであり、とりわけ「機能」を提供する「量」が減っていく以上、それを「質」の充実と「質」の豊富さでカバーし、凌駕していくことが求められるのではないでしょうか。
保育の質の向上や多機能化、連携・協働などと言われているのは、まさにそのことを別の言葉で表現していると言っていいでしょう。くり返しになりますが、保育の生きる道は、「機能」に着目して量から質への転換を図ることができるかどうかにかかっています。
★「保育ナビWebライブラリー」保育のいまがわかる!Webコラム 吉田正幸の保育ニュースのたまご vol.126(6月15日号)で配信した記事です。
★「保育ナビwebライブラリー」では、1か月早くお読みいただけます。