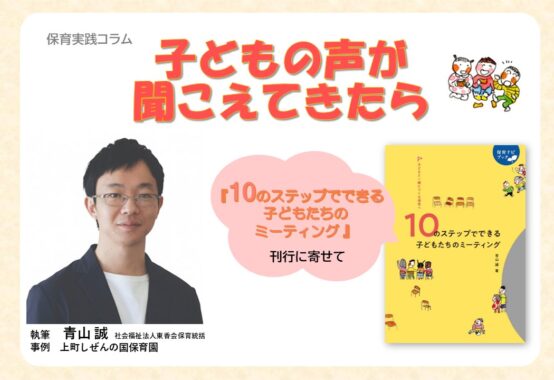◆ 毎回、これからの変化のきっかけにつながるかもしれない保育に関する様々な事柄を取り上げながら、独自の視点から分析します。
厚生労働省が先ごろ公表した人口動態統計速報(令和7年4月分)によると、今年1月から4月までの出生数は、すべての月で昨年の同じ月を下回っていることがわかりました。加えて、来年は60年ぶりに丙午(ひのえうま)の年が巡ってきます。
そう考えると、今後さらに少子化が進むことを前提に、これからの保育の在り方を模索することが大切になります。しかも、保育だけの閉じた在り方ではなく、地域共生社会という視点をもって、様々な分野との連携・協働・共生の可能性を探っていくことが求められます。また、既にそのための検討も少しずつ行われようとしています。
例えば、厚生労働省老健局が主催する「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会では現在、保育分野も含めた福祉サービスの在り方が検討されています。この検討会は、今年1月から開催されており、介護や地域包括ケアを中心に検討してきましたが、5月からは保育や障害にも対象を拡げて、社会福祉全体の問題として議論しています。
そのメンバーとして筆者も5月から参加しているのですが、直近の会議では保育分野について「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」という地域分類をベースに、「保育機能の維持・確保を進めていくため」の課題として、「保育所等の多機能化、法人間の連携、法人の合併や事業譲渡、統廃合等」などが挙げられています。
これらの課題については、こども家庭庁が2028(令和10)年度末を見据えて示した「保育政策の新たな方向性」においても、「人口減少地域における保育機能の確保・強化」として取り上げています。具体的には、教育・保育施設の計画的な統廃合や多機能化、合併・事業譲渡などが想定されています。
中長期的には、法人解散や施設閉鎖なども避けられないため、無用の混乱を避けながら縮小・撤退していけるソフトランディングの在り方も大きな課題となりますが、当面の方策としては多機能化や合併・事業譲渡が現実的な政策課題になると考えられます。
特に、多機能化については、比較的取り組みやすい方策であり、人口減少の程度を問わず、多くの教育・保育施設が積極的に検討すべき課題と言えます。行政としても、そのために必要な財政措置や規制緩和、参考となる事例の提示など、様々な支援策を進めていくのではないかと思われます。
ただ、多機能化を進めていこうとする際に大きなネックとなるのが、それぞれの教育・保育施設の基本的な考え方や姿勢です。大袈裟に言えば、各園の理念や哲学、原理原則と言ってもいいでしょう。幼稚園関係者(特に私学助成園)の中には、「園児を長時間預かったり、0・1歳から保育するのは好ましくない」「公費100%の給付を受けるのは私学としていかがなものか」など、保育所関係者の中には「1号子どもの受け入れは福祉ではない(だから認定こども園にはならない)」といった意見もいまだに聞かれます。
念のために申し上げておきますが、それが悪いといっているわけではありません。それぞれの信念や思いに基づいて教育・保育に携わることはリスペクトします。しかし、その強いこだわりは、一種の原理主義とも言えるもので、社会構造や社会経済の変化に抗う中で大切な本質を見失ってしまう危険性もはらんでいます。
普通に“こどもまんなか”の発想や視点に立てば、同時に数十年前とは様変わりした家庭や地域社会の変貌(機能低下)を考え合わせれば、様々な環境や状況に置かれた子どもたちに多様で柔軟な質の高い機能を提供することの必要性、重要性が浮き彫りになります。
わが子だと主張する2人の母親に対して、その子の腕を掴んで引き寄せるよう命じた大岡越前守。2人が一所懸命引っ張ったら、子どもが痛がって泣き出した。その時思わず手を離した母親が本物の母親だと認めた、という大岡裁きの噺があります。
話の真偽はともあれ、「だれのため」「何のため」という現実的な“大義”を尊重して、頑なな天動説に陥っていないか、時には自戒の念を込めて問うてみることも必要な時代を迎えているのではないでしょうか。
★「保育ナビWebライブラリー」保育のいまがわかる!Webコラム 吉田正幸の保育ニュースのたまご vol.128(7月15日号)で配信した記事です。
★「保育ナビwebライブラリー」では、1か月早くお読みいただけます。