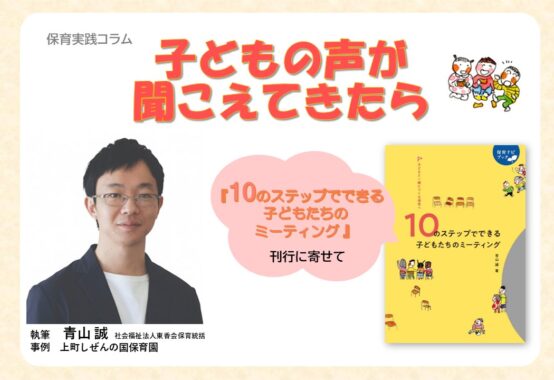◆ 毎回、これからの変化のきっかけにつながるかもしれない保育に関する様々な事柄を取り上げながら、独自の視点から分析します。
来年度からの本格実施を見据えて、「こども誰でも通園制度」の実施に向けた準備作業が進められつつあります。具体的な準備作業は、国・都道府県・市町村それぞれで異なりますが、実施主体である市町村が最も大変だとみられています。
特に難しいと思われるのが、利用が見込まれる未就園児のニーズ把握と必要量の推計、そして第3期市町村子ども・子育て支援事業計画への反映です。それぞれの市町村に満3歳未満児が何人いるかは把握できても、そのうち何割くらいがこの制度を利用するかを把握するのは容易ではありません。
今年度から始まった第3期 市町村子ども・子育て支援事業計画を策定する際、多くの市町村では子育て家庭に対するアンケート調査(ニーズ調査)を行いましたが、その中で「こども誰でも通園制度」の利用意向を尋ねたところはそれほど多くありません。しかも、当時の状況では、聞かれた保護者自身が新しい制度をよく理解できておらず、一時預かりとの区別もほとんどついていない中で回答していますので、適切なニーズ把握ができたとは言い難いのが実情です。
改めてニーズ調査を行うのが理想なのですが、どれだけの市町村が改めて調査を行うのかわかりません。そのための費用や時間を考えると、ニーズ調査を行わないところが多いのではないかと推察されます。
ニーズ把握に次いで難しいのが、その受け皿となる施設・事業者の確保です。利用ニーズを把握し、必要量を推計できたら、今度はそれに応じた受け入れ数を確保しなければなりません。市町村事業計画は、教育・保育や地域子育て支援の需要に応じた供給を確保するための需給計画ですから、こども誰でも通園制度の「量の見込み」と「確保方策」を計画に盛り込まなければなりません。その期間は、既に第3期事業計画が今年度から始まっていますので、2026年度から2029年度までの4年間となります。
こども誰でも通園制度を利用する乳幼児の量の見込みが正確に出せないのに、適切な供給確保方策を打ち出せるとは思えません。しかも、今回の制度では、地域子育て支援拠点や認可外保育施設、企業主導型保育施設、一時預かり事業所なども実施できます。
そのため、こども誰でも通園制度には、新しい認可制度(乳児等通園支援事業の認可)が取り入れられます。既存の認可施設の場合は、みなし認可で大丈夫だと思いますが、事業に取り組む認可外保育施設等ついては改めて認可を求める必要があります。
認可基準を条例で定め、認可に関する諸規定を整備して、認可に係る受付・審査を行うことになるため、それが完了するのは来年の2、3月頃になる見通しです。これでは、認可外保育施設等の量の見込みを正確に算定することはできません。ということは、遅くとも年内に見直しが行われる市町村事業計画への反映には間に合いません。
加えて、市町村における乳児等通園支援事業の認可に関しては、「必要利用定員総数及び利用定員の総和を勘案した需給調整の仕組み」が導入されるため、利用を希望する需要より供給が多いと予想される場合には、市町村が認可をしないという需給調整(供給抑制)が行われる可能性もあります。
それ以上に不透明なのが、認定こども園や保育所、幼稚園、小規模保育事業所といった既存の施設・事業者が、果たしてどのくらい未就園児の受け入れを積極的に行うかです。時間単位の給付単価がいくらになるのか、定期利用と自由利用の区別を施設主体で設定できるのか、市町村単独の上限時間引き上げや上乗せ補助はあるのかなど、様々な状況、条件が明らかにならない限り、簡単に手を挙げることはできないでしょう。
不透明な状況のまま、非常にタイトなスケジュールの中で、向こう4年間にわたる需要と供給の数を計画に盛り込み、着実に事業を進めていくことは、決して容易なことではありません。関心、期待、不安も多い事業だけに、運用面の課題を早く解決してほしいものです。
★「保育ナビWebライブラリー」保育のいまがわかる!Webコラム 吉田正幸の保育ニュースのたまご vol.130(8月15日号)で配信した記事です。
★「保育ナビwebライブラリー」では、1か月早くお読みいただけます。