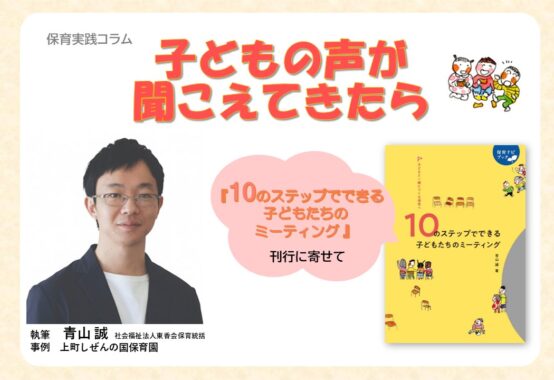◆ 毎回、これからの変化のきっかけにつながるかもしれない保育に関する様々な事柄を取り上げながら、独自の視点から分析します。
こども家庭庁は毎年度、子ども・子育て支援施策に関する調査研究事業を公募しています。この事業は、同庁がこれから取り組む施策に役立てたいと考えている諸課題について、調査研究によって有用な手掛かりや基礎資料を得ることを目的としています。
言い換えると、これら調査研究の各課題を通して、同庁がどのような施策に取り組もうとしているのか、何を重視しようとしているのか、政策の方向性を知る手掛かりになります。そんな視点から、今年度の公募テーマ(調査研究課題)を見てみると、今後の保育施策に関するものとして、次のような公募課題が挙げられています。
なお、これら調査研究に関しては、○○総研、○○研究所といった大手のシンクタンクや調査会社が事業を受託するケースが多く、採択に当たっては研究者らを中心とした企画評価委員会を設けて、そこで実施計画等の提案に対する事前評価と、年度末までにとりまとめた報告書等に対する事後評価という2段階審査が行われています(事前審査は終了)。
◇ 保育の質や保育所等の職員配置に係る指標の在り方に関する調査研究
◇ こども・子育て支援の地域分析に関する調査研究
◇ 保育所等の合併・事業譲渡等に関する実態調査
◇ 保育士の多様な働き方に関する調査研究
◇ 各保育所、認定こども園等における職員の資質の向上に係る調査研究
◇ 各保育所、認定こども園等における保育の内容面でのICT の活用に係る調査研究
◇ 企業主導型保育事業における地域の課題や充足率に関する調査研究
◇ 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の従事者への研修に関する調査研究
◇ 保育士等の意識及び業務負担軽減に関する調査研究(二次公募)
このうち、「保育の質や保育所等の職員配置に係る指標の在り方に関する調査研究」は、令和6年度調査研究事業(二次公募)に引き続き実施するもので、前年度に行った諸外国の文献調査や有識者等へのヒアリング調査を踏まえて、さらに深掘りするために必要なものについて追加的な調査を実施するというものです。
今回は、学識経験者等による調査チームを設置して、具体的な調査対象や手法等について検討を行い、来年度以降に実施する調査の設計を行うとされており、昨年度・今年度・次年度の3か年にわたる事業となっています。それだけ今後の政策課題として、保育の質や職員配置に関するエビデンスベースの調査研究成果を重視しているということだと思います。
ちなみに、公募内容では、調査方法について、① タイムスタディ、② 定量分析、③ バイタルチェックによる保育士のストレス分析等が想定されるとしており、調査方法ごとに具体的な調査設計を行うことが求められています。
「こども・子育て支援の地域分析に関する調査研究」については、2040年に向けて乳幼児人口の減少や一層の保育人材難が懸念されることから、保育に係る各種データを収集しながら地域分析を進めていくのが目的です。保育の現状や今後に関する基礎的なデータ集を作成するとともに、有識者等で構成する検討委員会を設置して、地域分析を進めるための調査票案の作成を行うことが求められています。従って、来年度も同事業を継続し、調査を実施しながら、地域分析を進めていくものと考えられます。
「保育所等の合併・事業譲渡等に関する実態調査」については、乳幼児人口の減少によって保育事業の継続が困難になるケースも想定されるため、保育機能の維持・確保に向けて事業者の協働化や合併、事業譲渡等による経営力の強化や円滑な事業承継が大きな課題とされています。その一方で、「事業譲渡等に関する情報や知見の不足、不適切なローカルルールによる予見性の低さや事務負担の重さが合併、事業譲渡等の弊害となっている」ケースも少なくないため、❶ アンケート調査やヒアリング等による合併・事業譲渡等に関する実態を把握する、❷ 研究会を設置し、調査結果等を踏まえて、ガイドライン等の作成・改訂の方向性を検討する、といった取り組みが求められています。
これらの動向は、文字通り「保育ニュースのたまご」と言えそうです。
★「保育ナビWebライブラリー」保育のいまがわかる!Webコラム 吉田正幸の保育ニュースのたまご vol.131(9月1日号)で配信した記事です。
★「保育ナビwebライブラリー」では、1か月早くお読みいただけます。