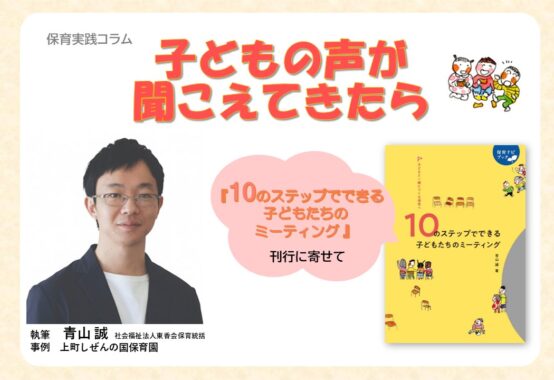「こどもまんなか社会」の実現に向けて、全国の園では様々な取り組みが行われています。そんな中、子ども、保育者、保護者など、関係するそれぞれのワクワクをいかに引き出すかは課題です。そこで『保育ナビ』公式WEBサイトでは、不定期ですが、子どものワクワクに焦点を当てながら、園での様々な保育実践を紹介していきます。

寄稿/佐藤康富(東京家政大学短期大学部 教授)
●プロフィール/佐藤康富(さとう やすとみ):東京家政大学短期大学部 教授。川崎市子ども・子育て会議 委員。著書に『写真とコメントを使って伝えるヴィジブルな保育記録のススメ』(鈴木出版)、『探究心を育む 保育内容「環境」』(大学図書出版)など。
★ 保育の様々な可能性を広げるドキュメンテーションについて、中野区立丸山保育園の事例を、子ども、保育者、保護者、それぞれのウェルビーイングの視点から解説します。【第2回】は保育者のウェルビーイングについてです。
3.保育者のウェルビーイング
最初は子どもの姿をよく観察して記録する「保育日誌の園内研修」がスタートだった。
そこから、保育者たちの中に「子どもたちがイキイキ遊んでいる姿を、タイムリーに伝えたい」という思いが膨らみ、写真を使った記録、ドキュメンテーションへの取り組みが始まった。
しかし、いざ始めてみると、「どんな写真がいいのか?」「タイトルはどうするのか?」「クラスだよりとドキュメンテーション、どう違うのか?」等々、疑問だらけ。
そんな時、丸山保育園の何人かの保育者が私の研修会に出会った。私が伝える「ドキュメンテーションを子どもに活かす」という視点に驚き、ドキュメンテーションに深くかかわることとなる。
そして、保育者たちに以下のような変化が見え始めた。
〈ドキュメンテーション5〉
手探り状態で始めたころ……
・ 子どもたちもドキュメンテーションを見ておもしろがる

ドキュメンテーションをどう作っていけばよいか手探りであったからこそ、保育者個人の作業でなく、保育者同士の情報共有が不可欠であった。
そこでは、「タイトルのつけ方」「子どものどのような場面を写真で切り取るとよいのか」「紙面のレイアウト・構成はどうすると効果的か」などが話し合われた。
しかしここで、ドキュメンテーションの共通フォーマットを作成して共有することはせず、各自が自由に取り組んだ。
結果的にこのことが、ドキュメンテーションのおもしろさ、工夫する楽しさに、保育者たちを開眼させる近道となった。
〈ドキュメンテーション6〉
1人の保育者のドキュメンテーションの変容


子どもの姿をドキュメンテーションにすることに目覚めた保育者は、初めはドキュメンテーションを出すことさえ戸惑いを見せていた。
しかしいつの間にか、子どもの「おもしろい姿」を見つけるやいなや1日に2回出したり、ほかのクラスの子どもの姿を見て、そのドキュメンテーションを作成したりする姿も見え始めた。
そして、ドキュメンテーションを作りたいと思った人が作れるよう、職員間で互いに協力し合うことが、クラスを越えて自然にできるようになった。
なぜこのような変化が生まれたのか。
それは、
・自由な形態のドキュメンテーション制作
・互いのドキュメンテーションの共有
に源泉があった。
文字だけのエピソード記録だと文章の上手さが際立つ。しかし、自由な取り組みのドキュメンテーション制作であれば、
・構成の上手さ
・子どもの姿を捉える写真のすごさ
・絵やレタリングで子どもの声を伝えるおもしろさ
など、保育者それぞれの個性が活かされ、互いがそれを尊重し合う姿勢が生まれる。
この姿勢は同僚だけでなく、子どもを見る眼にも活かされることになる。
協力/中野区立丸山保育園